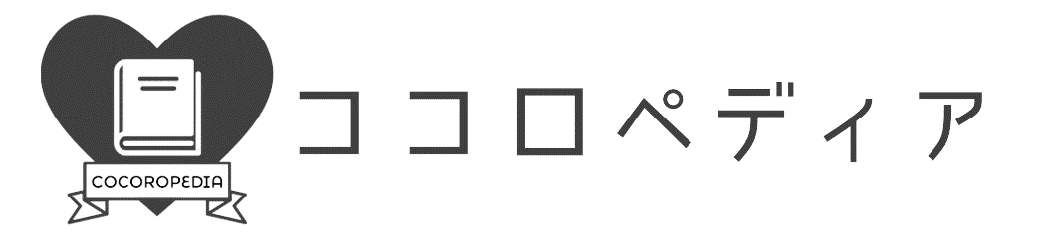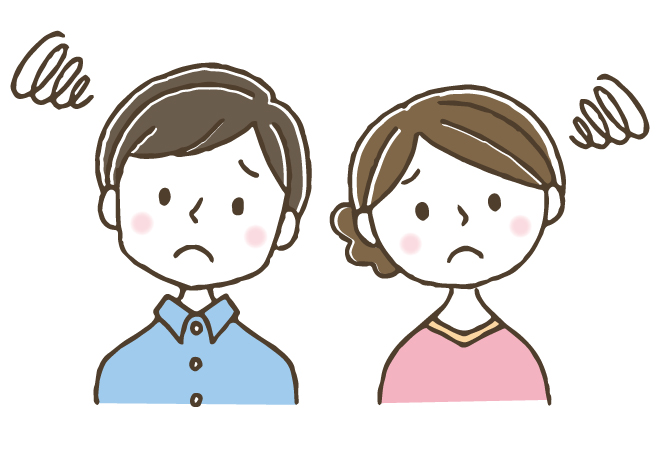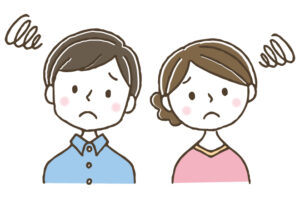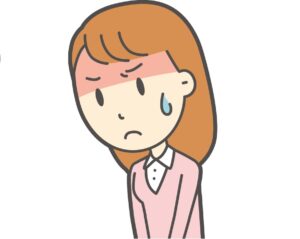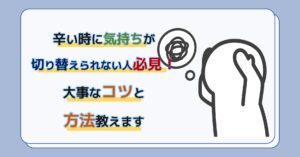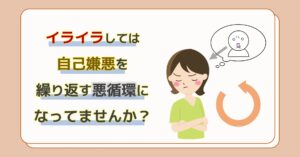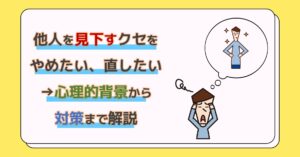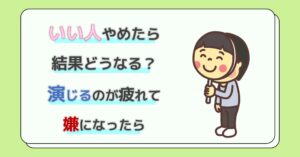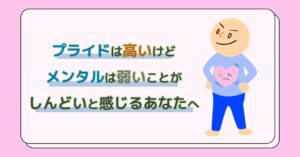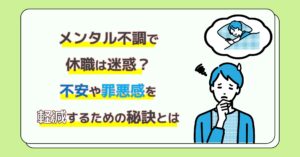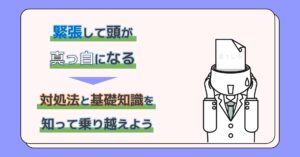こんにちは。
【オンライン心理カウンセリングなごやか】
心理カウンセラーのイヌカイです。
インターネット上のたくさんの情報の中から
この記事を選んでいただいてありがとうございます。
友だちや同僚に、親や家族に…
日常の何気ない場面から、
打ち合わせや会議の場で、
サークルや飲み会の場で…
言いたいことははっきりあって胸や喉のあたりまで来ているのは分かっているのに、
つい抑えてしまいストレスがたまってしまう。
いつもいつもこんな状態だととてもつらくなってきますし
「なんでこんなこともできないの?」って自分を責める口実にもなってしまいます。
そんな「言いたいことが言えない」悩みを解決するポイントは
「言うか言わないか」という二択から抜けること。
お悩みについてくわしい解説といっしょにお話していきます。
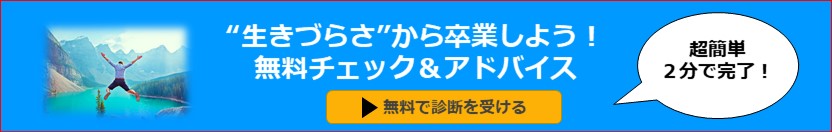
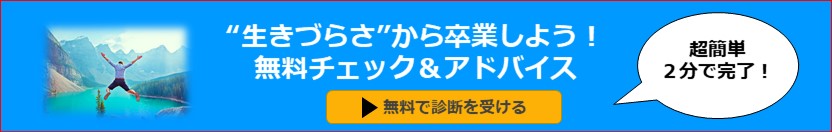
言いたいことが言えない状態は心の不調をまねく
言いたいことが頭に浮かんだのにほとんど出かかっていたのに、
ついつい抑えてしまい家に帰った後や人と別れた後などに、
延々と悶々としてしまうことってありませんか?
言えなかったそのこと自体も当然気になるし、
もしかするとだれかに主導権を握られてしまったりしたことで
実害をこうむってしまったなんてこともあるかもしれませんね。
なんにしたって、言いたかった言葉がずっと引っかかったままだし、
言えなかった自分に対して情けなくなってしまったり呆れてしまったり。
そんなことが続いて自分を責めることがクセになってしまったりすると、
憂うつな気分が抜けなくなって行動もしづらくなり、
ついには仕事や生活に支障をきたすようになることすらあるからちょっと怖い。
そんなふうになってしまうのは避けたいところですよね。
うん、でもだいじょうぶです。
正しい知識や原因や方法を知ることで改善していくことは
ぜんぜん可能ですから!
「言うことが受けいれられないとどうなる?」
考えたことはありますか?
結論から言っちゃいますね。
ほとんどの場合、「言いたいことを言えない」理由は、
「言いたいこと」を言ったがゆえに、
自分を否定・拒否・見下されることへの恐怖感があるからです。
実はけっこうシンプル。
細かい理由をあげれば
- 「相手を怒らせるのが怖い」
- 「空気が読めないと思われたくない」
- 「相手を傷つけてしまいそう」
などなどいくらでも出てくるでしょうけどね。
でも、行き着く先は結局いっしょじゃないですか?
自分が否定されたり、拒否されたり、低くみられたりすることが
とてつもなくつらいから、それを避けるために
「言いたいことを言わない」っていう選択をしてるんです。
言いたいことが言えなくて頭がぐるぐる悶々とし始めたら、
一度自分に問いかけてみてください。
「もしもあの時○○って言って□□って反応が返ってきてたら、
自分はいったいぜんたいどうなってしまうんだろう?」
何が何なのか、わけわからんものってやっぱり怖いじゃないですか。
自分が何を怖れているのかにサーチライトを当ててやるだけでも
ずいぶんと違ってきますよ。
“言える自分”になる2つのアプローチ


言いたいことを言える自分になっていくためには、
ざっくりと分けて2つの道すじが考えられます。
一つは前の節で説明した恐怖心を和らげていく道。
もう一つは伝え方を見直してトレーニングしていくという道。
前者は根本的な解決法のひとつではあるものの、
取り組んでいくのはかなり大変だし一人だけでやるのはきついです。
もちろんやったほうが、いいはいいに決まってるんだけど、
そこから始めてしまうとどうしても時間がかかるから
改善されてきた感が感じられる前に挫折してしまう可能性大。
だから、ちょっとむずかしいかなと。
挫折してしまうと「やっぱりダメじゃん…」って、
より苦手感が強化されてしまうのでそれはできれば避けたいところ。
なので後者のアプローチで「あ、ちょっといけた」という感覚を積み重ねて、
まずは“普段の自分”を強くしながら、
その後平行して恐怖感そのものに取り組んでいくっていうのが推奨です。
トレーニングを重ねていった結果、恐怖感は完全解決はできてないけど
「日常的には困ることがほとんどなくなったからこんなもんでいいや」
ってなっても別に全然OKです。
(私のセッションを受けていただくクライアントさんにも、本人が望まれるレベルを尊重しています。
強引に過去を深掘りさせたりして完全解決させようとかっていうのはやってません。)
「言う」「言わない」の2択じゃない
さらっと伝え方を見直して、とか書いちゃいましたが、
ここ、とっても大事なところです。
「言いたいことが言えなかった…(´・ω・`)」ってなると
どうしても「言ったか言わなかったか」という、
1か0かのデジタル思考におちいりがちだったりします。
ついでにもう一つ言うと、「言いたいことを言ったら相手を必ず〇〇…」
という思い込みもたいていありますね。
○○には「怒らせる」とか「傷つける」とか、
相手がマイナスな状態になるようなことが入ります。
ここで注意してほしいことは、『必ず』っていう前提に気づくことです。
よーく考えてみましょう。
この世の中。人間に関わることで『必ず!』とか『絶対!』起こることって
そうめったになくないですか?
・
・
ないですよね(・∀・)
はいはいはい!そんな必死に探してもないですって!(笑)
ほとんどの場合において、人間に関することは□□なときもあれば、
△△なときもあるっていうのが当たり前なんですけど、
ついつい同じ経験が続いたりすると『必ず』『絶対』『常に』『全て』
こんなふうに感じるようになっていってしまうものなんです。
これも いきものの サガか…
(元ネタ分かる人は歳がバレます。)
まあ、割合はいつも5:5ではないですけどね。
7:3だったり9:1だったりはしますよ。
それでも10:0なんてまずないです。
じゃあ。あなたがもしも相手に言いたいことを言ったとして、
それがどうなるかは分からない。
どういうふうにとらえるかは相手の問題だから。
もっといえば同じ相手に同じ言い方をしたとしても、
その相手の機嫌の良し悪しでとらえられ方は変わってしまいます。
どうせ完璧にはできないんですよ。
できることは、確率の高いほうを選んでいくだけ。
相手をマイナスな状態にしないであろう言い方を
できるだけ心がけていくことです。
そう、大事なのは言い方・伝え方であって『言うか言わないか』ではないのです。
もちろんあえて沈黙を示すという高度な選択肢も状況によっては有効ですが、
意図的に沈黙を使いこなせるようになるには、
言いたいことを言えるという状態にある程度なれている必要があります。
言い方・伝え方を考えてみる


「勇気を出して言ってみよう!」って思えたときに、
せっかくなら相手をマイナスな状態にしない可能性が高い方法を
選べるようにしていきたいですよね。
自分も相手も大事にしつつ言いたいことを言うことを
心理学の用語でアサーションと言います。
くわしく解説している本やサイトもたくさんあるので
深く学びたい方は調べてみてもいいかもですね。
一応、超ざっくりとご説明すると、
コミュニケーションにおいては
- アグレッシブ(攻撃的)
- ノンアサーティブ(非主張的)
- アサーティブ
という3つのタイプがあります。
1は相手の気持ちとか都合とか考えずにひたすら自己主張をするタイプ。
エヴァンゲリオンのアスカとかイメージしやすいでしょうか。
2は自分の言いたいことはぐっと押しとどめて相手に合わせてしまうタイプ。
こちらはシンジくんですね。
この記事を一所懸命読んでいただいているあなたは多分このタイプが近いんでは?
そして、3は相手のことを大事にしつつ、自分の言いたいことはちゃんと伝えると言うタイプ
この3番を目指そうよというのがアサーションです。
と紹介しておいてなんですがトレーニングとしてまずやる必要があるのは、
「伝え方・言い方」の方法とか技術ではありません
じゃ、一体なにから取り組んだらいいのかといいますと
・
・
・
それは
『まず先に相手を受け入れる』ということです。
どうしても、『言いたいことを言う』という視点で見ていると、
自分がどうしたらいいかだけに目がいってしまいます。
細かい伝え方のテクニックうんぬんの前に
相手がどんな人でどんな理由でこの主張をしていて、
どんな気持ち・感情を持って話をしているのか
といったことに思いをはせて、相手を理解することにつとめることが大事です。
そこまでやったうえで自分の主張ができれば、
細かいテクを使わなくてもそんなひどいことにはよっぽどなりませんよ。
相手が嫌いとかじゃなくても、ただなんとなく一方的に
怖いとか苦手とか怒りそうとか傷つきそうとかの印象を勝手にもって、
「言いたくても言えない」って思っているのは、
ある意味では相手に対して失礼とも言えますよね。
もちろん、とにかく勝手に恐怖感がわいてくるということもあります。
過去の恐怖や不安に引っ張られてしまうパターンですね。
そこに心当たりがあるようならこちらの記事↓も参考になると思います(^_^)


言いたいことが言えるようになると


「言いたいこと」があるのに言うことをガマンしてるのって、
察知能力がそこそこ高い人には意外とカンタンにバレちゃうんです。
そうすると逆に相手をイラつかせることも。
「こいつ腹になにか持ってるな」って不信感を抱かせることまでありえますよ。
だから、言いたいことを言えるようになると心の健康だけじゃなくて、
現実の人間関係がスムーズになっていろんなことが突然動き出したりしますよ。
もしも抵抗感・恐怖感とかがめちゃめちゃ強くて、
なんともならないようならカウンセリングなどの利用を検討してもいいと思います。
ほんのちょっとでも今よりできるようになればまさにプライスレス!
取り組む価値は十二分にあるテーマです。
あなたが言いたいことをしっかりと伝えつつ、
相手とのステキな関係をつくれるようになることを応援しています。
最後までお読みいただきありがとうございます。
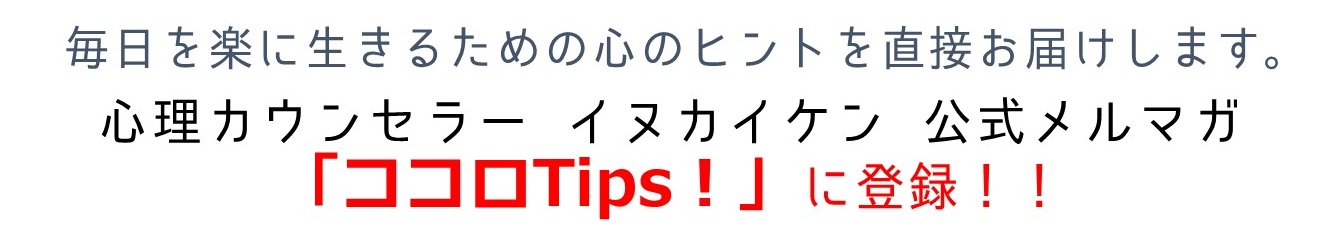
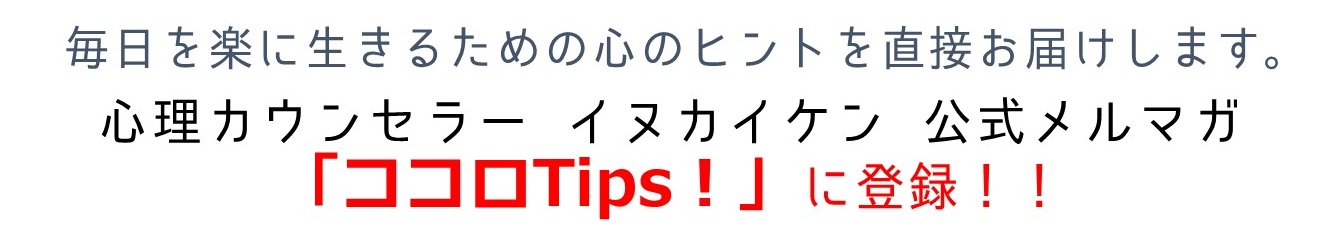
(購読の解除はメールのリンクをクリックするだけでいつでも可能です。)
(最近、無料版Gmailのアドレスに届かない事例が多発しております。
現時点では設定などで対応ができないようですので、
登録確認メールの返信が1時間以上経ってもない場合は
他のメールアドレスをご利用いただくことをおすすめいたします。)